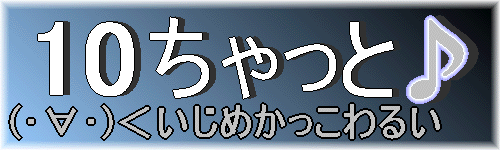【1:29】
いじめの後遺症
- 1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/09(Sun) 16:51
- いじめに遭って、後遺症が残ってしまった人のスレッドです
身体的な後遺症ではなく、精神的な後遺症です
・自分に自信が持てなくなった
・人が怖い(対人恐怖症等)
・周りの視線が気になって外に出れない
・当時と同じようなシチュエーションになると動機が激しくなって恐怖を感じる
等、精神的な後遺症は残ります
カウンセリングで症状が軽くなる場合はありますが完治は難しいです
そして私にも後遺症はあります
自分に自信が持てません
周りと比較すると、やはり異常です
此処は傷をなめ合う場ではなく、少しずつ治していく手助けをする場です
- 20 名前:松堀不動産 投稿日:2024/12/02(Mon) 14:41
- 新型コロナ関連倒産-株式会社松堀不動産(埼玉県東松山市)が破産決定(創業50年以上の不動産会社)
株式会社松堀不動産(埼玉県東松山市、1973年2月、資本金10,000万円、堀越 宏一社長)は11月18日、地方裁判所熊谷支部より破産開始決定を受けた。
破産管財人には伊島 博 弁護士(伊島法律事務所、埼玉県東松山市)が選任された。負債総額は約19,500万円。
株式会社松堀不動産は1973年2月創業の不動産業者で、不動産仲介、売買等を手掛け、2018年10月期は8,126万円の売上高を計上していた。
しかし、その後は新型コロナウイルス感染拡大に伴う外出自粛の影響等で業績は伸び悩み、宅地分譲にも着手したものの、販売面は苦戦を強いられていた模様。
また、昨今の物価高も加わり採算的にも厳しい経営が続いていたもので、資金繰りも限界に達し、今回の事態に至った。
(2024年11月18日 毎日新聞)
- 21 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2025/05/15(Thu) 08:12
- 株式会社オキムスの星川薫はクソ人間
いじめ大好き
パワハラ大好き
不倫大好き
チビで歯が 汚いメガネ
- 22 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2025/05/18(Sun) 00:07
- オキムス確定
星川ハゲヲ
つるっぱげ
- 23 名前:まさゆき 投稿日:2025/06/01(Sun) 09:21
- 1986年、神戸市立垂水中学校。当時私は3年10組でした。
私は「北斗の拳ごっこ」と称して、同級生から日常的に暴力を受け続けました。
理由などなく、ただ面白半分で殴られ、蹴られ、心の奥深くにまで傷を刻まれるような日々でした。
来る日も来る日も、私は恐怖の中で生きていました。そして次第に、「悪いのは自分なのだ」と思い込むようになっていきました。
誰かに助けを求める勇気など、持てませんでした。
担任のロイヤーは、いじめの現場を目にしながらも見て見ぬふりを決め込み、私は完全に孤立していきました。
やがて、クラスの他の生徒たちからも冷たい視線を向けられ、ツバを吐きかけられ、黒板消しで制服を汚されました。
学生帽を溝に捨てられる。パンツを脱がされ、蹴られる。日々繰り返される嫌がらせと暴力。
子どもだった私は、それをただ耐えるしかなかった。心を麻痺させ、理不尽を受け入れることで、なんとか毎日をやり過ごしていたのです。
本当は泣きたかった。助けてほしかった。
けれど、誰ひとり、手を差し伸べてはくれませんでした。
あれから、40年近くが経ちました。
けれど、あのときの痛みと屈辱は今も私の心に棲みついたままです。
社会人として生きながらも、心のどこかは、今もあの寒々とした教室に閉じ込められたままでした。
怖くて、誰も信じられなくて、ふとした瞬間に記憶がよみがえり、心をえぐるのです。
その果てに、私は10年間、引きこもりの生活を送りました。
誰とも会わず、誰とも話さず、社会から姿を消した時間。
窓の外の世界を見ながら、「自分の居場所は、もうこの世界にはない」と、心を閉ざして生きていました。
社会に戻ることは、絶望にも似た恐怖でした。
外に出ること、人と目を合わせること、その一歩一歩が崖を登るような挑戦でした。
それでも私はあきらめたくなかった。壊れた心を抱えながらも、世界の中にもう一度立つために、必死で闘いました。
そして、最近ようやく気づいたのです。
あの頃、自分を責め続けていたけれど、悪かったのは私ではなかった。
私を殴り、笑い、傷つけたのは、あの加害者たちだったのだと。
長い年月をかけて、ようやくその呪いから、少しだけ自由になれたのです。
私はその思いをすべて言葉にして、掲示板に投稿しました。
同じように苦しんでいる誰かに、私の声が届けばと願って。
しかし、加害者の実名を記したことで、名誉毀損の容疑をかけられ、須磨署の警察が二度にわたり自宅を訪れました。
その後、神戸地検に2度出頭し、計70万円の罰金を科されました。
いじめに苦しみ続けた末、ようやく声を上げた私に、社会は「罰」という形で応えたのです。
なぜ、傷つけられた者が、さらに傷つけられなければならないのでしょうか。
なぜ、加害者たちは何の責任も問われず、何の償いもなく、平然と生きているのでしょうか。
この国にとっての「正義」とは、一体何なのでしょう。
(省略されました・・全てを読むにはここを押してください)
- 24 名前:まさゆき 投稿日:2025/06/04(Wed) 07:38
- あの日の朝のことは、一生忘れません。
2022年6月13日(月)。
何気ない日常の一コマ、いつものように職場に出勤したはずでした。
けれど――その朝、私の人生は突如として「容疑者」として扱われる側に変わったのです。
ベージュの日産エクストレイル。
私服姿の警察官が数名、静かに、しかし確実な目的を持って私の職場に現れました。
彼らは、迷いなく私のもとへ歩いてきて、こう告げました。
「後藤さん?ちょっと来て。警察や。」
その瞬間、私の心臓は強く脈打ち、全身の血が逆流するような感覚に襲われました。
彼らは無言で水色の警察手帳を広げ、私を囲むように立ちました。
「何も変な物持ってへんな」――軽く身体検査。
そして、キャノンの一眼レフカメラが無言で私を捉え、シャッター音だけが響きました。
「荷物ここに持って来て。逮捕せえへんから。何で警察来たか心当たりたるか?
インターネットの掲示板に書き込みせんかったか?あれ、名誉毀損にあたるねん。
今から署に来れる?それか、仕事が終わった後、須磨署に来れる?」
私は震えていました。
手も足も心も凍りついて、ただ「はい」と頷くしかなかった。
でも、それはまだ序章に過ぎませんでした。
彼らは、仕事が終わった私の自宅にもやってくると告げたのです。
そして夜。
私は、何事もなかったかのように玄関を開けました。
するとそこにいたのは、アルファードに乗ってやってきた6名の警察官たち。
まるでドラマのワンシーンのようでした。
彼らは無言で家に上がり込み、淡々とインターネット環境を調べ、私の中学の卒業証書を手に取り、それを写真に収めました。
2時間。
自宅は尋問室のように変わり果て、私は何も言えずにただ見つめるだけ。
彼らは、すべてを“証拠”に変えながら、やがて静かに去っていきました。
だが、これで終わりではなかった。
後日、須磨警察署に出頭を命じられました。
朝9時から夕方17時半まで――丸一日かけての取り調べ。
(省略されました・・全てを読むにはここを押してください)
- 25 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2025/06/15(Sun) 13:41
-
【告発文】
声をあげた者が罰せられる国で、誰が真実を語れるのか
1986年、神戸市立垂水中学校。私は同級生から「北斗の拳ごっこ」と称した暴力を、日常的に受けていました。殴られ、笑われ、他の同級生からは唾を吐かれ、パンツを脱がされ、帽子を溝に捨てられる――担任教師も見て見ぬふり。子どもだった私は、耐えるしかありませんでした。
その痛みは、40年近く経った今も消えません。心の中の教室に、私はまだ閉じ込められています。
苦しみ続けた末、ようやく私は気づきました。「悪いのは自分ではなかった」。そしてその想いを言葉にし、加害者の名前とともにネット掲示板に投稿しました。誰かに届けばと願って。
しかし、返ってきたのは社会からの「罰」でした。
警察が家に来て、「掲示板に名前を書いたから名誉毀損だ」と告げられました。神戸地検に呼び出され、罰金70万円。いじめの事実を語っただけなのに、私は犯罪者にされたのです。
どうして、こんなことが許されるのでしょうか?
いじめを訴える声が処罰され、加害者は何の責任も問われず、のうのうと暮らしている。
それが、この国の「正義」なのでしょうか?
(省略されました・・全てを読むにはここを押してください)
- 26 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2025/06/22(Sun) 22:53
- 『未来世紀ブラジル』の素晴らしさ――夢と抑圧、ユートピアとディストピアの狭間で
『未来世紀ブラジル(Brazil)』は、元モンティ・パイソンのテリー・ギリアム監督によって1985年に発表されたSF映画である。公開当時から高い評価と激しい議論を呼び、現在ではカルト的名作として映画史に深く刻まれている。この作品が放つ独特の魅力は、単なる未来社会の風刺にとどまらず、夢と現実、個と集団、自由と管理という根源的な人間のテーマを、異常なまでに緻密で奇怪な映像世界を通して表現している点にある。
物語の主人公はサム・ローリーという一介の役人。彼は高度に官僚化され、全体主義的に管理された社会の中で、淡々と働きながらも心の奥では夢想に耽る日々を送っている。現実は、行政によるミスが原因で無実の市民が逮捕・死亡しても誰も責任を取らず、それを訂正しようとする者はむしろ不審者とされるような社会だ。サムは偶然にも、夢に現れる“翼のある理想の女”ジルに似た女性と出会ったことから、現実に抗おうとし、やがては体制そのものから逸脱していく。
この映画の最大の特徴は、圧倒的な“ビジュアルの異様さ”である。レトロなタイプライターや真空管、無数のパイプとダクト、意味不明な標語が書かれたポスターがひしめくオフィスや街並み――これは明らかに現代の延長ではなく、「20世紀中盤の未来予想図がそのまま時間を止めてしまった」ような、奇妙なレトロフューチャーである。この造形は決して単なる様式美ではなく、「技術の進歩=人間の自由の拡張」ではなく、「技術の進歩=抑圧の強化」という皮肉を、観客の視覚に直接叩きつけるための手段として機能している。
物語のトーンは、ブラックユーモアとファンタジーと絶望が混在する奇妙なものだ。官僚社会を描く中で、ギリアムは笑いを誘う滑稽さをあえて挿入するが、それは笑っていいのかすら不安にさせる不気味さを孕んでいる。たとえば、顔面整形を受け続けて皮膚が溶けていく老婦人や、壊れたパイプを修理する“非合法配管工”ハリー・タトル(ロバート・デ・ニーロ)など、登場人物たちは一様に狂気と無関心の狭間で生きている。そして、それが決して他人事でないことを観客に突きつけてくる。
本作のタイトル『ブラジル』は、あの有名なサンバの名曲に由来しており、映画の中でも繰り返しメロディが流れる。しかし、その明るくのどかな旋律は、どんなに悲惨で無意味な場面にも差し込まれ、希望と絶望が音楽を通じて反転し続ける。まるで「人間の心の中の自由」はどれほど閉塞した世界でも生きているのだと訴えているかのようであり、同時に「その自由は夢に過ぎない」という虚無のメッセージにも感じられる。この二重性こそが、ギリアムの最大の才能である。
サムの見る“夢”は、翼を持って空を飛び、美しい女性を救い、悪を打ち砕くヒーロー的幻想だが、それはあくまで現実の過酷さから逃避するためのものであり、決して実現することはない。物語の最後、サムは体制によって完全に捕らえられ、拷問の末に“現実”からも心を切り離し、夢の中で幸福に飛翔していく。観客はその姿に一瞬救いを感じるが、それが「精神崩壊による永遠の逃避」であることに気づいた瞬間、言いようのない喪失感に襲われる。
『未来世紀ブラジル』が真に恐ろしいのは、描かれている社会が荒唐無稽な未来像ではなく、むしろ現代社会の縮図である点にある。役所の形式主義、責任のたらい回し、マスメディアによる誘導、監視社会、個人の自由よりも“システムの正当性”が優先される世界。テリー・ギリアムが提示したディストピアは、単に恐怖を煽る未来像ではなく、「いま、ここで起こっている事実を拡大し、風刺的に可視化した世界」にほかならない。
また本作は、1984年のオーウェル的監視社会や、カフカ的な官僚迷路、さらにはフェリーニ的な夢と現実の交錯を想起させるなど、さまざまな芸術的影響を巧みに融合している。だが、それを単なる模倣ではなく、ギリアム独自の“ビジュアル詩”として昇華している点に、彼の作家性の強さがある。
結末は観る者によって解釈が分かれる。「夢の中で自由に生きる彼は救われた」のか、それとも「現実から逃げただけで、完全な敗北なのか」。答えは与えられない。ただ確かなのは、サムが“夢を見ること”をやめなかったという事実であり、それこそがこの映画の最後の希望でもある。
- 27 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2025/06/22(Sun) 23:55
- 朱に交わればハゲになる
- 28 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2025/06/23(Mon) 05:15
- 宮崎駿監督による2001年のアニメーション映画『千と千尋の神隠し』は、日本のみならず世界中で高い評価を受け、アカデミー賞長編アニメ賞を受賞するなど、日本アニメの枠を超えて世界的な文化遺産としての地位を確立した作品である。本作の素晴らしさは、その豊かな物語性、象徴性に富んだ世界観、そして細部にまでこだわり抜いた作画と音楽、さらには成長物語としての普遍的な力強さにある。
まず、この作品は単なる「不思議な世界で少女が冒険する」物語にとどまらない。10歳の少女・千尋が、両親とともに引っ越し先へ向かう途中、不思議な世界に迷い込み、両親が豚にされてしまう。彼女はそこで湯屋で働くことを強いられ、「千」と名前を奪われる。ここから始まる彼女の物語は、「アイデンティティの喪失と回復」、「労働と自己肯定」、「善悪の相対化」など、多くの現代的かつ深遠なテーマを内包している。
特に「名前を奪われる」描写は、日本古来の信仰に通じる部分がある。名前は魂の一部とされ、それを奪うことはその人自身の本質を支配することに等しい。湯婆婆によって「千尋」から「千」へと名前を変えられる千尋は、まさに現代社会における自己喪失の象徴だ。しかし彼女は物語を通じて他者との関係性の中で自分を取り戻していく。このプロセスは、自己確立を目指す成長譚であり、子供だけでなく大人にとっても深い共感を呼ぶ。
もう一つの特筆すべき点は、作品全体に流れる「曖昧さ」と「グレーゾーン」の存在である。典型的な善人や悪人は登場せず、どのキャラクターも一面的ではない。たとえば湯婆婆は権力的で厳格な存在だが、赤ん坊のボウを溺愛するという母性を見せる。一方で、姉の銭婆は見た目こそ同じだが、穏やかで優しく、千尋を導く存在として描かれる。また、「カオナシ」という存在も、当初は無垢で純粋な存在として登場するが、千尋への執着や湯屋での混乱を引き起こすなど、非常に複雑なキャラクターである。人の心の裏表、欲望と孤独の表現としてカオナシは象徴的な存在となっており、観る者に「本当の自分とは何か?」を問いかける。
こうしたキャラクターたちの多面性は、現代社会に生きる私たちが直面する多様な価値観や、人間関係の複雑さを映し出している。勧善懲悪ではなく、「何が正しいか」を自分で見極め、判断していく必要があることを物語は示している。
さらに本作の美術的な完成度の高さも語らずにはいられない。湯屋の設計や、食べ物の描写、異界の風景に至るまで、すべてが緻密で説得力がある。特に、八百万の神々が湯屋に集う場面では、日本の神道文化を背景に持ちながらも、どこか異国的な不思議さも漂わせており、見る者の想像力をかき立てる。そこには「失われつつある日本」のノスタルジーがあり、それを体感的に感じることができる。
音楽面でも、久石譲による楽曲は物語の感情の流れを完璧に補完している。特にピアノで奏でられる「あの夏へ」や、千尋とハクの別れのシーンで流れる「ふたたび」などは、映像と一体化し、観る者の心を震わせる。音楽は決して出しゃばらず、それでいて深く心に残る。まさにアニメーション作品における音楽の理想的なあり方がここにある。
また、『千と千尋の神隠し』は「環境問題」や「消費社会への警鐘」というメッセージも内包している。冒頭で両親が見知らぬ店の料理を食べて豚になる場面は、まさに「無自覚な貪欲さ」が引き起こす代償を象徴している。過剰な欲望は人間を動物にしてしまうという警句は、現代の私たちにも強く響く。
物語の終盤、千尋はハクの本当の名前を思い出し、彼を縛る契約を解き放つ。この瞬間、名前と記憶の力、そして他者への深い共感がいかに世界を変えるかが示される。人と人との関係性の中でこそ、自分という存在は明確になっていくという思想が、この映画の根底にある。
そして最後に、千尋がトンネルを抜けて元の世界に戻るシーン。そこでの彼女の表情には、もはや最初の不満げな少女の面影はなく、凛とした静かな強さが漂っている。これは千尋が「旅」を通じて確かに成長した証であり、観客もまた彼女とともに一つの通過儀礼を経験したような気持ちになる。
総じて、『千と千尋の神隠し』は、子どもの成長物語としても、大人への寓話としても読むことができる多層的な作品である。視覚・聴覚・感情のすべてに訴えかける芸術性を持ちながら、それでいて物語は普遍的で、どの時代にも通じる。だからこそ、この映画は何度観ても新しい発見があり、観る者の人生のフェーズによって響くポイントが変わる。「本当の自分」を探し、「大切なもの」を守るために成長していく千尋の姿に、私たちは勇気と希望をもらえるのだ。
- 29 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2025/06/28(Sat) 17:41
- 株式会社オキムスの公社住宅事業部
星川薫はいじめ、パワハラ、不倫、人権侵害大好きな
チビで歯が汚いメガネ
いじめ、パワハラ、不倫をするために生を受けた明らかな欠陥品、害虫
-
|